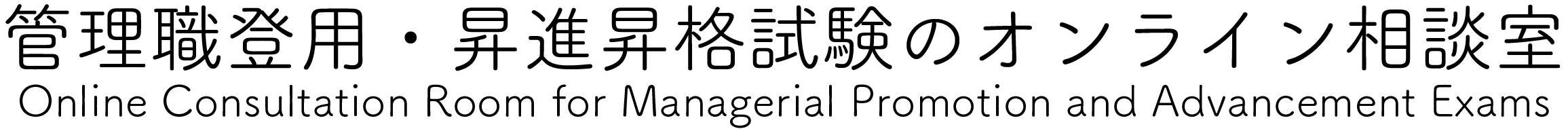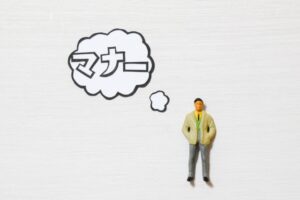はじめに:時間がない中での筆記試験対策は本当に大変!
昇進・昇格試験の準備に関して多くの人が直面する壁──それは「時間が足りない」という現実です。
私自身も子育て真っ只中の時期に昇格試験を受けることになり、日々の業務に追われながら家事育児の合間の限られた時間で試験の準備をしなければならない……そのような経験をしました。
以前、下記の記事にて昇進昇格に関する各種試験の簡単な解説をしました。
今日は、各種試験の中から特に範囲が広く時間がかかる【筆記試験】に関する対策について詳しく解説していきます。

筆記試験は、マークシート形式で幅広い知識を問われるケースが多く、決して一夜漬けでは通用しない内容です。
出題範囲も広く、経営管理・財務会計・人事労務など、ふだんの業務ではあまり触れない分野もカバーしなければなりません。
しかしながら、限られた時間のなか模索しながら取り組んだ経験は今となっては大きな財産です。
この記事では、筆記試験で問われる内容の傾向や、忙しい人でも実践できる効率的な学習法について、自身の経験を交えながらお伝えしていきます。
出題される科目とその傾向を把握しよう
① 代表的な出題科目
昇進・昇格試験の筆記問題は、「幅広いビジネス知識がバランスよく備わっているか」を確認するために設計されていることが多く、単なる暗記力だけではなく、思考力や理解力も求められます。
代表的な出題科目としては、以下のようなものが挙げられます。
- 経営管理:経営戦略やマーケティング、組織論など
- 財務会計:貸借対照表や損益計算書の基本、原価計算、利益分析など
- 人事労務:労働基準法、人事評価制度、モチベーション理論など
- 一般常識:世界情勢や経済、時事問題など
これらに加えて、企業によっては以下のような分野も出題対象となることがあります。
- 英語:ビジネスメールの読解や簡単な英文法など
- 業界・社内知識:自社のビジネスモデルや業界動向、過去のプロジェクト内容など
② 実際に出題される問題の例
次に、実際に出題される問題のイメージも確認してみましょう。
- [財務会計]
次のうち、貸借対照表の負債の部に該当するものはどれか。
A. 売掛金 B. 支払手形 C. 資本金 D. 減価償却累計額 -
B. 支払手形
- [人事労務]
労働基準法において、法定労働時間は原則として1日何時間、1週間何時間と定められているか。
A. 8時間、40時間 B. 9時間、45時間 C. 8時間、44時間 D. 7時間、35時間 -
A. 8時間、40時間
- [経理管理]
SWOT分析の「T」に該当する要素として適切なのはどれか。
A. 社内の強み B. 業界のチャンス C. 市場の脅威 D. 顧客ニーズ -
C. 市場の脅威
③ 筆記試験対策の第一歩
これまで見てきたように、筆記試験の出題科目や出題範囲は多岐にわたります。
そのため、すべてを完璧に覚えようとするとどれも中途半端になってしまいがちです。
まずは、自社で出題される科目とその範囲を把握することが最初の重要な一歩です。
過去問そのものは試験時に回収されることが多く入手は難しいかもしれませんが、
先に昇格した先輩に聞いてみたり、社内の研修資料や社報などから情報収集したりすることが有効です。
その上で、どこを重点的に学ぶべきかを見極めることが、限られた時間の中で成果を出すカギになります。
限られた時間をどう使う?スケジュールの立て方
では、ここからは具体的な試験対策のスケジューリングについて私自身の体験談も踏まえて解説していきます。
時間がない人こそ、戦略的に進めることが合格への近道になります。
① 全体を見て“優先順位”をつける
出題範囲を見たとき、すべてを網羅しようとすると挫折します。
まずは前章でお伝えしたように、出題傾向を把握し「出そうなところ」と「自分が苦手なところ」を洗い出してみましょう
一般的には、「得意分野の点数を伸ばす」より「苦手分野を少しでも克服する」方を優先すべきです。
理由は2つあります。
- 科目ごとに足切り(合格に必要な基準点)がある場合、苦手科目を放置してはいけないため
- 得意分野の細部に拘るより、苦手分野の基本を習得した方が点数が伸びやすいため
このように、得点に繋がりやすい「タイパの高い学習」を意識しましょう。
② スキマ時間を“習慣”に変える
特に育児中などで忙しい方はまとまった勉強時間がとれない場合も多いかと思います。
しかしながら、「今度の土曜日にまとめてやろう」などと考えてしまうと、勉強開始が遅れ残り期間もどんどん減ってしまいます。
こういう方におすすめなのは、毎日の生活の中のスキマ時間を活用することです。
- 通勤中に音声教材を聞く
- 子どもを寝かしつけた後の15分だけテキストを開く
- お昼休みに1問だけ例題を解いてみる
ポイントは、「短くても毎日やる」ことです。たとえ15分でも、1ヶ月積み重ねれば約7時間半になります。
この積み重ねが、合格ラインへの地道な力になります。
③ 試験日から逆算して、ゆるくでも“計画”を立てる
完璧なスケジュールでなくてもOKです。
「この週は財務会計」「来週は人事労務」など、1週間単位でテーマを決めるだけでも、迷わず勉強に取り組めるようになります。
もし計画を立てずに進めてしまったら、「思ったより時間が取れず、直前期にやろうと思っていた苦手科目に着手できなかった」などの大きな失敗に繋がりかねないです。
なお、「計画を立てたけど崩れた…」という日があっても大丈夫。
そのときは潔く休んで、次の日にリスタートすればOKです。大事なのは、止まらずに続けることです。
育休復帰2年目での昇格試験体験談
ここからは私の体験談をお話します。
私が係長試験(組合員の最上位等級、管理職の一つ手前)を受けたのは育休から復帰して2年目のことでした。
プロフィールにも書いてある通り、実は、復帰後1年目の昇格試験を受けられない、という苦い経験があります。
本当はこの1年目を見送られたときから、翌年に向けて準備をしていればもっと余裕を持った準備ができていたと思います。
ですが、当時の私は日々仕事に子育てに忙殺され、結局試験準備を始めたのは2年目で実際に試験を受けられることがわかってからでした
試験までに残された期間は1ヶ月半・・・。

この記事では短期的な対策について解説していますが、忙しい方ほど長期的な準備がおすすめです。例えば、数年以内に試験が受けられそうだとわかっている場合は、語学や時事など範囲が広く自身の成長にもつながる科目をコツコツ始めるのが◎です。
① 出題科目
当時私が受けた筆記試験の科目は以下の通りです。
- 人事労務
- 財務会計
- 時事問題
- 英語
- 業界・社内常識
実は、昇格試験としては筆記試験以外にも小論文試験・面接試験もあったためそちらの準備も並行して行っていました。
今回は筆記試験にしぼって私が実際に行った対策をご説明いたします。
② 自分の得意・苦手分野を考慮した対策
試験の科目を踏まえ、以下のような方針を立て実行しました。
- 1.人事労務
-
長年人事部に所属していましたので、今ある知識のみで戦うことを決めました
直近の法改正など、出題されやすそうなところのチェック程度は行いましたが、勉強はほぼしませんでした。 - 2.財務会計
-
ここが一番の苦手科目でした
筆記試験対策のうち、全体の6~7割の時間を割きました。
対策としては、財務会計の基本の参考書1冊完了させました。(簿記3級のテキストでもいいと思います)
財務会計の出題範囲は次の時事問題等に比べると狭いため、直前期の対策が有効だったと思います。
実際に、苦手科目だったにもかかわらず8割程度は点がとれました。 - 3.時事問題
-
財務会計の次に心配な科目でした。
当時、育休から復帰して2年目だったこともあり、テレビ・ニュースといったものから大きく遠ざかっていたためです。
不安ではありましたが、出題範囲が広いため、時間をかけすぎても点数は伸びないだろうと考えました。そのため、対策としては、時事に関する書籍を1冊買い全体を浅く広く理解するように努めました。
筆記試験対策のうち、全体の1~2割の時間を割きましたが、実際の問題では事前学習の内容があまり出題されず、勉強の効果はイマイチだった記憶があります・・・。 - 4.英語
-
当時の私のTOEICの点数は650点ほどでした。
決して得意な方ではありませんでしたが、短期的に点数を伸ばすのは難しいと考えたため対策は特にしませんでした。
本来は、語学のような科目は長期間かけてコツコツ取り組むのが効果的だと思います。 - 5.業界・社内常識
-
この科目は、ほとんど研修や社内資料に基づき出題されることが予告されていました。
得点源となり得る科目でしたので、研修資料の暗記や社内資料の理解に1~2割の時間を割き、実際に満点近い点数がとれたと記憶しています。
以上が、当時の私が実行した対策です。
短い準備期間ではありましたが、自分の得意分野・苦手分野を把握し、効率よく準備ができたと思います。
結果として、当時の同じ等級の受験者の中で筆記試験はTOP通過することができました。
(当時、受験者に全体の順位等は開示されていませんでしたが、人事部所属であったため上長からフィードバックがありました。)
また、すべての科目において80点以上得点することができました。
当時の試験は科目別の足切りはなく、合計点で基準を満たしていればOKだったのですが、苦手科目がなく平均的に点数をとれていた点を、当時の部長・本部長からも評価いただくことができました。
まとめ:試験勉強は未来の自分の武器になる
昇進・昇格試験の筆記対策は、合格するために必要な努力です。
ですが、実はそれ以上に、「未来の自分を支えてくれる土台づくり」でもあります。
私自身、昇格前は財務会計に対して苦手意識を抱えて勉強していました。
でも、いざ管理職になってみると、会社の決算内容の理解やそれに基づく方針立案、予算管理など、これらの知識が非常に重要であることをあらためて理解しました。
あのときの勉強がなければ、管理職としての仕事を理解するスピードも全く違っていたと感じています。
時間がない中での学習は大変です。
でも、そんな日々の積み重ねが、“できる自分”という実感に変わる瞬間が、きっとやってきます。
昇進や昇格はゴールではなく、次のステージへのスタートです。
あなたの新たな挑戦を応援しています!